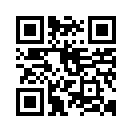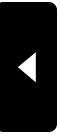2015年05月27日
5/26 ハートフルガーデナー・園芸福祉おおつ 植え替え作業に参加しました。
スタッフの牧野(=^・^=)です!
「未来ファンドおうみ助成事業2015」の採択団体の活動が始まっています!!
淡海ネットワークセンターでは、採択団体の進捗状況等を把握するために、各団体担当者が年3回程度のヒアリングと採択事業に参加しています。
5月26日(昨日)、未来ファンドおうみ助成事業2015「びわこ市民活動応援基金」の採択団体である「ハートフルガーデナー・園芸福祉おおつ」さんの植え替え作業に参加してきました。
「ハートフルガーデナー・園芸福祉おおつ」さんは、花と緑を通して、幸せを地域に拡げる園芸福祉活動を大津市内で展開しようと、園芸を愛する有志で、2008年1月に結成されました。
2015年度は、未来ファンドおうみの助成を受け、身障者の授産通所施設と高齢者が通うディケアセンター2か所に設けた花壇の花苗の植え付けを通所者と一緒に行います。また、花壇経営を休む冬季の2月には「園芸学習会」を開催されます。
今回は大津市立晴嵐デイサービスセンターでの植え替え作業です。


5月下旬とも思えない日差しの強い日でしたが、10名のメンバーの方々が参加されて、植えるための穴を掘り、水を撒いて苗を置くという準備を進めていらっしゃいました。


左の赤い花が「日日草」、右が「ペンタス」だと思います。(ネットで検索しましたが、確信は持てません。。。)
今回は、お二人の施設利用者の方が植え替え作業に参加され、メンバーの方々が優しくご指導されていました。


施設利用者の方たちとの交流を深めながら、幸せを地域に拡げる園芸福祉活動が今年も展開されます。
「未来ファンドおうみ助成事業2015」の採択団体の活動が始まっています!!
淡海ネットワークセンターでは、採択団体の進捗状況等を把握するために、各団体担当者が年3回程度のヒアリングと採択事業に参加しています。
5月26日(昨日)、未来ファンドおうみ助成事業2015「びわこ市民活動応援基金」の採択団体である「ハートフルガーデナー・園芸福祉おおつ」さんの植え替え作業に参加してきました。
「ハートフルガーデナー・園芸福祉おおつ」さんは、花と緑を通して、幸せを地域に拡げる園芸福祉活動を大津市内で展開しようと、園芸を愛する有志で、2008年1月に結成されました。
2015年度は、未来ファンドおうみの助成を受け、身障者の授産通所施設と高齢者が通うディケアセンター2か所に設けた花壇の花苗の植え付けを通所者と一緒に行います。また、花壇経営を休む冬季の2月には「園芸学習会」を開催されます。
今回は大津市立晴嵐デイサービスセンターでの植え替え作業です。
5月下旬とも思えない日差しの強い日でしたが、10名のメンバーの方々が参加されて、植えるための穴を掘り、水を撒いて苗を置くという準備を進めていらっしゃいました。
左の赤い花が「日日草」、右が「ペンタス」だと思います。(ネットで検索しましたが、確信は持てません。。。)
今回は、お二人の施設利用者の方が植え替え作業に参加され、メンバーの方々が優しくご指導されていました。
施設利用者の方たちとの交流を深めながら、幸せを地域に拡げる園芸福祉活動が今年も展開されます。
2014年08月08日
虎御前山古墳と中世城郭保全顕彰会へ訪問
8月6日、虎御前山古墳群見学会が行われました。
この虎御前山には、数多くの古墳群が点在していますが、多くは
未調査になっています。
地元では環境保全と史跡の顕彰を行い、文化遺産を後世に伝えようと
市民の方々が、取り組んできました。
年2回の枝打ち、下草刈りや、案内・説明板の取り付けなど、
子どもにも声をかけながら活動されています。
本日は、信長B支群の測量が終わったので、現地見学会が開催されました。
虎御前山は南北に長い山で、昔は長尾山といったそうです。
場所は長浜市虎姫町から湖北町へ渡っています。


この日は蒸し暑い日で、少し歩くだけで汗が流れますが、皆さん、資料を手に
熱心に聞かれていました。


白いテープが貼ってるのが測量のあとです。



子どもたちも含め、大勢の参加者でした。

この虎御前山には、数多くの古墳群が点在していますが、多くは
未調査になっています。
地元では環境保全と史跡の顕彰を行い、文化遺産を後世に伝えようと
市民の方々が、取り組んできました。
年2回の枝打ち、下草刈りや、案内・説明板の取り付けなど、
子どもにも声をかけながら活動されています。
本日は、信長B支群の測量が終わったので、現地見学会が開催されました。
虎御前山は南北に長い山で、昔は長尾山といったそうです。
場所は長浜市虎姫町から湖北町へ渡っています。

この日は蒸し暑い日で、少し歩くだけで汗が流れますが、皆さん、資料を手に
熱心に聞かれていました。
白いテープが貼ってるのが測量のあとです。


子どもたちも含め、大勢の参加者でした。
2013年10月22日
どろんこキッズ農体験
9月28日、青空の下米原市近江町で活動されている
どろんこの会の収穫祭が行われました。
どろんこの会は、子ども達に農業を通して何かしてあげたいと考え、
地域のおじいちゃん、おばあちゃんが立ち上がり、結成された団体です。
この日は稲刈りとサツマイモの収穫です。
子ども達の参加は37名、ボランティアさんが12名、
そのほか子ども達の親や兄弟で大勢の参加でした。


カマを持って稲を刈り、昔の脱穀機を体験します。
稲の持ち方、釜のあて方、足の位置など丁寧に教えられていました。


子ども達は初めての子も多いのですが、稲をひとつかみして、
力を込めてカマを当てていました。
脱穀は足も使わなくてはいけませんが、力がいりますから、難しかったようです。

サツマイモの収穫は、土が堅いので大きな芋はなかなか採れなくて、大勢で
土を掘っていました。でも大きな芋が採れると、自分がとったということで
自慢です。


その後、公民館に帰り、露天風呂体験や、遊びをして過ごします。
いつもは露天風呂も畑のそばのハウスでされていたそうですが、今回は
先日の台風で、ハウスが水につかり、水道が使えなくなったということで
急遽、午後の部は公民館で開催となったということです。


このあたりは田園風景の田んぼが広がっていますが、新興住宅地も多くなって
田植えや畑の体験など、したことがない親子も多いそうです。そういうこともあり、どろんこの会の皆さんは、子ども達に農業体験を通していろいろなことを学んでほしいと思い、地域のおじいちゃん、おばあちゃんとして活躍されています。
どろんこの会の収穫祭が行われました。
どろんこの会は、子ども達に農業を通して何かしてあげたいと考え、
地域のおじいちゃん、おばあちゃんが立ち上がり、結成された団体です。
この日は稲刈りとサツマイモの収穫です。
子ども達の参加は37名、ボランティアさんが12名、
そのほか子ども達の親や兄弟で大勢の参加でした。


カマを持って稲を刈り、昔の脱穀機を体験します。
稲の持ち方、釜のあて方、足の位置など丁寧に教えられていました。


子ども達は初めての子も多いのですが、稲をひとつかみして、
力を込めてカマを当てていました。
脱穀は足も使わなくてはいけませんが、力がいりますから、難しかったようです。

サツマイモの収穫は、土が堅いので大きな芋はなかなか採れなくて、大勢で
土を掘っていました。でも大きな芋が採れると、自分がとったということで
自慢です。


その後、公民館に帰り、露天風呂体験や、遊びをして過ごします。
いつもは露天風呂も畑のそばのハウスでされていたそうですが、今回は
先日の台風で、ハウスが水につかり、水道が使えなくなったということで
急遽、午後の部は公民館で開催となったということです。


このあたりは田園風景の田んぼが広がっていますが、新興住宅地も多くなって
田植えや畑の体験など、したことがない親子も多いそうです。そういうこともあり、どろんこの会の皆さんは、子ども達に農業体験を通していろいろなことを学んでほしいと思い、地域のおじいちゃん、おばあちゃんとして活躍されています。
2012年12月02日
エコツーリズム協会しがの「畑の棚田」ツアーのご報告
スタッフの坂下です。
先月、未来ファンドおうみ「びわこ市民活動応援基金」の助成団体であるエコツーリズム協会しがさんのツアーが開催されましたので参加してきました。
11月10日(土)、「にほんの棚田百選 畑の棚田 へ行こう~懐かしい風景と暮らし・食を訪ねる旅~」が開催され、高島市畑地区を訪ねました。
畑地区の棚田は「日本の棚田百選」に指定されています。
お迎えいただいた棚田を守る地元の方から、棚田の保全にかける思いをお聞きしました。
現在の畑地区は高齢化率47%。棚田を守る就農者の平均年齢は70歳以上。最高齢は92歳現役!だそうです。先祖から受け継ぎ、子孫から預かる棚田を自分たちだけで守ることは難しい状況の中、棚田オーナー制度やボランティア、大学や企業と連携し、持続的な保存の仕組みを工夫しておられます。
平成11年に棚田百選に指定されてから、地域の保全への意識が高まり、地域外の力を借りて保全をしていこうとオーナー制度を作られました。当初60人弱のオーナーから始まったこの制度、毎年どんどん増えて今年は286人のオーナーによって支えられているそうです。田植えと稲刈りだけの参加の方やあぜ塗りなどの作業にも来られるこだわりオーナーさん、収穫されたお米からできたお酒がお土産になる酒オーナーなど、オーナーのメニューも豊富です。
お話をお聞きしていると、棚田オーナーに登録したくなります。
地域の魅力を引き出し、地域の人と来訪者との交流がエコツーリズムの魅力です。

昼食は地元のお母さん方の手作り伝統料理です。お味噌は棚田米の味噌、冬瓜のあんかけ、お肉はイノシシの肉、大根と柿の和え物、コゴミのサラダ、お漬け物は大根や白菜を塩と唐辛子だけで漬ける「棚田漬け」。

お料理のお話や畑地区の四季折々のお話などお聞きしながら、ゆっくりとお昼をいただきました。

午後から地区の中を散策。まずは、農家民泊をされているお家を訪ねました。見晴らし抜群。軒にぶら下がる干し柿も絵になります。

農家民泊は、ご家族と一緒に日常を過ごさせてもらうホームステイのようです。旅館やホテルでは作れない、地域の方との交流と思い出ができるでしょうね。

棚田の間を散策しています。

見晴らしのいい所から紅葉と棚田の風景を楽しみました。

四季折々の風景を見に来たい所です。

少人数の参加で、じっくりとお話をお聞きしながらの散策でした。

地元の方にご案内いただき、地域の魅力を十分に味わい、楽しめた旅でした。
エコツーリズム協会しがでは、滋賀県の他の地域でもエコツアーを計画されているそうです。
ぜひ、滋賀県の各地の魅力を地域の方々と一緒に発信していただきたいと思います。
先月、未来ファンドおうみ「びわこ市民活動応援基金」の助成団体であるエコツーリズム協会しがさんのツアーが開催されましたので参加してきました。
11月10日(土)、「にほんの棚田百選 畑の棚田 へ行こう~懐かしい風景と暮らし・食を訪ねる旅~」が開催され、高島市畑地区を訪ねました。
畑地区の棚田は「日本の棚田百選」に指定されています。
お迎えいただいた棚田を守る地元の方から、棚田の保全にかける思いをお聞きしました。
現在の畑地区は高齢化率47%。棚田を守る就農者の平均年齢は70歳以上。最高齢は92歳現役!だそうです。先祖から受け継ぎ、子孫から預かる棚田を自分たちだけで守ることは難しい状況の中、棚田オーナー制度やボランティア、大学や企業と連携し、持続的な保存の仕組みを工夫しておられます。
平成11年に棚田百選に指定されてから、地域の保全への意識が高まり、地域外の力を借りて保全をしていこうとオーナー制度を作られました。当初60人弱のオーナーから始まったこの制度、毎年どんどん増えて今年は286人のオーナーによって支えられているそうです。田植えと稲刈りだけの参加の方やあぜ塗りなどの作業にも来られるこだわりオーナーさん、収穫されたお米からできたお酒がお土産になる酒オーナーなど、オーナーのメニューも豊富です。
お話をお聞きしていると、棚田オーナーに登録したくなります。
地域の魅力を引き出し、地域の人と来訪者との交流がエコツーリズムの魅力です。
昼食は地元のお母さん方の手作り伝統料理です。お味噌は棚田米の味噌、冬瓜のあんかけ、お肉はイノシシの肉、大根と柿の和え物、コゴミのサラダ、お漬け物は大根や白菜を塩と唐辛子だけで漬ける「棚田漬け」。
お料理のお話や畑地区の四季折々のお話などお聞きしながら、ゆっくりとお昼をいただきました。
午後から地区の中を散策。まずは、農家民泊をされているお家を訪ねました。見晴らし抜群。軒にぶら下がる干し柿も絵になります。
農家民泊は、ご家族と一緒に日常を過ごさせてもらうホームステイのようです。旅館やホテルでは作れない、地域の方との交流と思い出ができるでしょうね。
棚田の間を散策しています。
見晴らしのいい所から紅葉と棚田の風景を楽しみました。
四季折々の風景を見に来たい所です。
少人数の参加で、じっくりとお話をお聞きしながらの散策でした。
地元の方にご案内いただき、地域の魅力を十分に味わい、楽しめた旅でした。
エコツーリズム協会しがでは、滋賀県の他の地域でもエコツアーを計画されているそうです。
ぜひ、滋賀県の各地の魅力を地域の方々と一緒に発信していただきたいと思います。
2012年10月05日
NPO法人かじやの里で寄せ植え教室がありました。
9月22日、東近江市のNPO法人かじやの里で、かじや村民大学「寄せ植え教室」が開催されました。

実習にあたって説明を受けました。

皆手際よく次々に形になっていきます。



作品ができあがりました。

実習の後山野草について講義を受けました。

お正月に向けては、また寄せ植え教室をされるそうです。
かじや館では、このような「かじ屋村民大学」でいろいろな講座を行い
地域の居場所になっています。
実習にあたって説明を受けました。
皆手際よく次々に形になっていきます。
作品ができあがりました。
実習の後山野草について講義を受けました。
お正月に向けては、また寄せ植え教室をされるそうです。
かじや館では、このような「かじ屋村民大学」でいろいろな講座を行い
地域の居場所になっています。