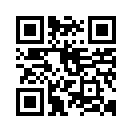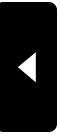2012年09月16日
9/16おうみ未来塾一般公開講座「地域と共に創る」を開催しました!
今回は、地域プロデューサーを目指す塾 おうみ未来塾12期生で入塾式を除くと基礎実践コース唯一の一般公開講座です。塾生30名に加え、一般からは14名の参加があり、今回のテーマの「地域と共に創る」とあるように塾生と一般の方々が「共に」地域づくりについて理解を深めるよい機会となりました。ご参加いただいた皆様どうもありがとうございました。
講師は、おうみ未来塾アドバイザーもしていただいているNPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表の藤井絢子さん、そして山梨県北杜市で都市農村交流で農村再生を実現されておられるNPO法人えがおつなげての代表 曽根原久司さんです。
流れとしては、滋賀県にはるばるこられた曽根原さんのゲスト講演が30分、そのあとは、場所は違えど共に農村をつなぎ地域と共に、地域を創ってこられたお二人の豪華スペシャル対談、1時間ですすみます。
まず、曽根原さんのゲスト講演ですが、タイトルがインパクトがあります。
「日本の田舎は宝の山~農村資源を都市のニーズと結べば、10兆円産業が動き出す~」です!まさに曽根原さんがNPO法人えがおつなげてで実践されてきたことがこのタイトルの中につまっています。

[講演中のNPO法人えがおつなげて 代表理事 曽根原久司さん]
ほんとに10兆円?動き出すのか?!そんな疑問の中、曽根原さんの明るい軽快なトークで農村再生ストーリーが進んでいきます。
荒れた耕作放棄地。全国的にも問題となっている問題ですが、曽根原さん移住された山梨県北杜市も例外ではありません。曽根原さんは、都市から若者や企業研修を受け入れ、外部資源を投入しながら放棄地の再生をされていきました。この輝かしい実績ですが、とても戦略的に計画された農村起業だったということがあとの12期生限定の曽根原さんの農村起業ワークショップでわかりました。農村資源と都市のニーズをかけあわせることで農村再生ビジネスモデルがうまれるということである。
そして、曽根原さんの講演のあと、いよいよ藤井さんと曽根原さんの対談です。対談のテーマは「地域と共に創る~食とエネルギーの自立にむけて~」です。

[お二人の対談の様子。左から藤井絢子さんと曽根原久司さん]
お二人は、同じくして食とエネルギーという暮らしの中で重要なものを自立に向かわせる仕組みづくりに力を入れておられます。
藤井さんは、菜の花を栽培し、その菜種油で出た廃食油でバイオディーゼル燃料にや石鹸にリサイクル。菜の花プロジェクトで食とエネルギーを循環させ持続可能な社会に向けて、この仕組みを地域から社会へ広げて行かれました。
お二人は、東日本大震災を契機に食とエネルギ―を地域で持続可能にしていくことの重要性をとなえながら、それぞれの活動経験からこれからの地域と共に創っていく仕組みについてのヒントを会場へ伝えていただきました。
淡海ネットワークセンターでは、おうみ未来塾など地域づくりに関する学びを講座をこれから開催していきますので、これからもどうぞよろしくお願い致します!

[最後に参加した塾生と一緒に元気もりもり~ポーズで記念撮影。地域プロデュースもりもり~やりましょう!]
講師は、おうみ未来塾アドバイザーもしていただいているNPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表の藤井絢子さん、そして山梨県北杜市で都市農村交流で農村再生を実現されておられるNPO法人えがおつなげての代表 曽根原久司さんです。
流れとしては、滋賀県にはるばるこられた曽根原さんのゲスト講演が30分、そのあとは、場所は違えど共に農村をつなぎ地域と共に、地域を創ってこられたお二人の豪華スペシャル対談、1時間ですすみます。
まず、曽根原さんのゲスト講演ですが、タイトルがインパクトがあります。
「日本の田舎は宝の山~農村資源を都市のニーズと結べば、10兆円産業が動き出す~」です!まさに曽根原さんがNPO法人えがおつなげてで実践されてきたことがこのタイトルの中につまっています。

[講演中のNPO法人えがおつなげて 代表理事 曽根原久司さん]
ほんとに10兆円?動き出すのか?!そんな疑問の中、曽根原さんの明るい軽快なトークで農村再生ストーリーが進んでいきます。
荒れた耕作放棄地。全国的にも問題となっている問題ですが、曽根原さん移住された山梨県北杜市も例外ではありません。曽根原さんは、都市から若者や企業研修を受け入れ、外部資源を投入しながら放棄地の再生をされていきました。この輝かしい実績ですが、とても戦略的に計画された農村起業だったということがあとの12期生限定の曽根原さんの農村起業ワークショップでわかりました。農村資源と都市のニーズをかけあわせることで農村再生ビジネスモデルがうまれるということである。
そして、曽根原さんの講演のあと、いよいよ藤井さんと曽根原さんの対談です。対談のテーマは「地域と共に創る~食とエネルギーの自立にむけて~」です。

[お二人の対談の様子。左から藤井絢子さんと曽根原久司さん]
お二人は、同じくして食とエネルギーという暮らしの中で重要なものを自立に向かわせる仕組みづくりに力を入れておられます。
藤井さんは、菜の花を栽培し、その菜種油で出た廃食油でバイオディーゼル燃料にや石鹸にリサイクル。菜の花プロジェクトで食とエネルギーを循環させ持続可能な社会に向けて、この仕組みを地域から社会へ広げて行かれました。
お二人は、東日本大震災を契機に食とエネルギ―を地域で持続可能にしていくことの重要性をとなえながら、それぞれの活動経験からこれからの地域と共に創っていく仕組みについてのヒントを会場へ伝えていただきました。
淡海ネットワークセンターでは、おうみ未来塾など地域づくりに関する学びを講座をこれから開催していきますので、これからもどうぞよろしくお願い致します!

[最後に参加した塾生と一緒に元気もりもり~ポーズで記念撮影。地域プロデュースもりもり~やりましょう!]
2012年08月09日
8/7おうみ未来塾12期生サブ講座「塾生交流会」を開催しました!
スタッフの膽吹(いぶき)です。
おうみ未来塾12期生もどんどん地域のフィールドで実践の中で学んでいます。
今回は8月7日に開催された、おうみ未来塾12期生サブ講座「塾生交流会」をご紹介します。
サブ講座とは、基礎実践コースの中の事務局が骨格を用意する本講座とは違い、塾生が主体的に企画をし
関わっていく講座になります。
今回は12期生、第一回目のサブ講座ということで事務局から卒塾生との交流を提案をして開催することになりました。
これまでの全体塾生会や世話人会などで、この塾生交流会で卒塾生にどのようなことを聞きたいかということ
議論しながら講座づくりをすすめてきました。
そもそものこの講座を12期生でする目的としては、おうみ未来塾は2年目になると、創造実践コースという地域課題解決のための実践活動に入って行くので、その経験を卒塾生から聞いて参考にさせていただくいうところにありました。おうみ未来塾のおもしろいところですが、一緒に学ぶ塾生30人がどうやってグループにわかれていくのか、グループをつくるという過程も学びなのです。地域をひとつのコミュニティと考えるとその中で合意を得ながらグループをつくり市民活動をしなければならないケースが多く出てきます。おうみ未来塾ではグループづくりをとおして地域活動を学んでいきます!もちろんグループをつくったあとは実際に地域に入り地域課題解決のための実践活動に入るわけですから、さらに実践的になります。
さあ今回はどのような話が卒塾生から聞けたのでしょうか?
今回の会場となったのは大津百町館というまちづくりを行う大津の町家を考える会の拠点施設をおかりしてのサブ講座です。
卒塾生である11期生の風かおるさんが会場のコーディネートを。司会進行は、12期生の運営サポーター 小久保弘さん(5期生)にお願い致しました。

[最初は私から今回の趣旨を説明です。町家の雰囲気がいい感じです。]

[11期生の風かおるさんから大津百町館について少し解説]

[みんなで自己紹介を回しながら、卒塾生からは当時していたグループ活動についてお話がありました。]

[みなさん真剣にメモを取りながら話を聞いています。]

[話をしながら質問も出てきます。]

[そして話をし合ったあとは、ご飯を食べながらの交流会です。気軽に塾生同士の交流できる雰囲気に一気に変わりましたね。]

[料理も地元商店街のこだわりの品々。かなり特盛りサービスでした。卒塾生の風さんがつくられてきた地域との関係もうかがえます。]

[最後に記念撮影!レトロな雰囲気の中とてもいい写真です。]
最後に、今回サブ講座としてははじめての塾生交流会でしたが、これから地域を変えて様々な卒塾生の方と交流をしながらネットワークを広げていけるような会にしていければ思います。また運営についても現役生の12期生と話し合いながらよりよいものをつくっていければと思います。
現在、おうみ未来塾の卒塾生は1~11期生までで261名です。県内、様々な地域で様々な形で地域課題解決に関わっておられます。これからの出会いを楽しみにしたいです。
おうみ未来塾12期生もどんどん地域のフィールドで実践の中で学んでいます。
今回は8月7日に開催された、おうみ未来塾12期生サブ講座「塾生交流会」をご紹介します。
サブ講座とは、基礎実践コースの中の事務局が骨格を用意する本講座とは違い、塾生が主体的に企画をし
関わっていく講座になります。
今回は12期生、第一回目のサブ講座ということで事務局から卒塾生との交流を提案をして開催することになりました。
これまでの全体塾生会や世話人会などで、この塾生交流会で卒塾生にどのようなことを聞きたいかということ
議論しながら講座づくりをすすめてきました。
そもそものこの講座を12期生でする目的としては、おうみ未来塾は2年目になると、創造実践コースという地域課題解決のための実践活動に入って行くので、その経験を卒塾生から聞いて参考にさせていただくいうところにありました。おうみ未来塾のおもしろいところですが、一緒に学ぶ塾生30人がどうやってグループにわかれていくのか、グループをつくるという過程も学びなのです。地域をひとつのコミュニティと考えるとその中で合意を得ながらグループをつくり市民活動をしなければならないケースが多く出てきます。おうみ未来塾ではグループづくりをとおして地域活動を学んでいきます!もちろんグループをつくったあとは実際に地域に入り地域課題解決のための実践活動に入るわけですから、さらに実践的になります。
さあ今回はどのような話が卒塾生から聞けたのでしょうか?
今回の会場となったのは大津百町館というまちづくりを行う大津の町家を考える会の拠点施設をおかりしてのサブ講座です。
卒塾生である11期生の風かおるさんが会場のコーディネートを。司会進行は、12期生の運営サポーター 小久保弘さん(5期生)にお願い致しました。

[最初は私から今回の趣旨を説明です。町家の雰囲気がいい感じです。]

[11期生の風かおるさんから大津百町館について少し解説]

[みんなで自己紹介を回しながら、卒塾生からは当時していたグループ活動についてお話がありました。]

[みなさん真剣にメモを取りながら話を聞いています。]

[話をしながら質問も出てきます。]

[そして話をし合ったあとは、ご飯を食べながらの交流会です。気軽に塾生同士の交流できる雰囲気に一気に変わりましたね。]

[料理も地元商店街のこだわりの品々。かなり特盛りサービスでした。卒塾生の風さんがつくられてきた地域との関係もうかがえます。]

[最後に記念撮影!レトロな雰囲気の中とてもいい写真です。]
最後に、今回サブ講座としてははじめての塾生交流会でしたが、これから地域を変えて様々な卒塾生の方と交流をしながらネットワークを広げていけるような会にしていければ思います。また運営についても現役生の12期生と話し合いながらよりよいものをつくっていければと思います。
現在、おうみ未来塾の卒塾生は1~11期生までで261名です。県内、様々な地域で様々な形で地域課題解決に関わっておられます。これからの出会いを楽しみにしたいです。
2012年08月03日
8/2第3回おうみ未来塾12期生世話人会開催しました!
スタッフの膽吹(いぶき)です。
おうみ未来塾12期生の第3回世話人会を開催しました!
おうみ未来塾は地域の課題解決をしていく地域プロデューサーを目指す市民が集う塾です。
場所は守山交流センターさんで。いつもお世話になっております。
本当は世話人会は12期生の地域ブロックでわかれているグループの世話人が話し合う会なので
最大で8人なのですが、なんとなんとみなさんの積極的な参加で
全体で14人!(+ちびちゃん2人)でした!
ちょっと世話人会というより縮小版の全体塾生会みたいな雰囲気で
わきあいあいと、塾生同士が塾活動をどうするかについて話し合いました。
主な議題はどうグループ分けをすすめるか。
おうみ未来塾では2年目になると、より実践的にグループにわかれて
それぞれが地域に入り、地域課題解決のために動きます。
で、どう30人の塾生がグループに分かれていくか。
それは1年目から自主的に計画をたてて話し合っていく必要があるのです。

[12期生の第3回の世話人会の円卓会議風景。真剣です!]

[イエ―イ!お疲れさまでした。記念写真です。]
塾生同士がこれからいい雰囲気で活動されていくと思いました。
12期生はこれからも元気に活動していきます!
みなさま応援のごどどうぞよろしくお願い致します!
おうみ未来塾12期生の第3回世話人会を開催しました!
おうみ未来塾は地域の課題解決をしていく地域プロデューサーを目指す市民が集う塾です。
場所は守山交流センターさんで。いつもお世話になっております。
本当は世話人会は12期生の地域ブロックでわかれているグループの世話人が話し合う会なので
最大で8人なのですが、なんとなんとみなさんの積極的な参加で
全体で14人!(+ちびちゃん2人)でした!
ちょっと世話人会というより縮小版の全体塾生会みたいな雰囲気で
わきあいあいと、塾生同士が塾活動をどうするかについて話し合いました。
主な議題はどうグループ分けをすすめるか。
おうみ未来塾では2年目になると、より実践的にグループにわかれて
それぞれが地域に入り、地域課題解決のために動きます。
で、どう30人の塾生がグループに分かれていくか。
それは1年目から自主的に計画をたてて話し合っていく必要があるのです。

[12期生の第3回の世話人会の円卓会議風景。真剣です!]

[イエ―イ!お疲れさまでした。記念写真です。]
塾生同士がこれからいい雰囲気で活動されていくと思いました。
12期生はこれからも元気に活動していきます!
みなさま応援のごどどうぞよろしくお願い致します!
2012年07月29日
【概要】おうみ未来塾12期生第2回本講座 余呉町合宿 報告!
淡海ネットワークセンターの膽吹です。
7/21、22と2日間にかけて、おうみ未来塾12期生の合宿をしてきました。
場所は長浜市余呉町。長浜市に合併をした余呉町では、市民によるまちづくりが活発に行われています。
今回のテーマは、「地域プロデューサーを考える」。
様々な余呉における地域プロデューサーの事例を見せていただきながら
塾生同士で地域プロデューサーとは何かを考える濃い2日間となりました。
一日目の午前中は、株式会社余呉バスに乗り込み、余呉のまちを見ていきます。
余呉バスの社長 木下さんに自ら運転いただく未来塾ならではのスペシャルなフィールドワーク。
公共交通は、経営難で撤退していく現実もあるなか、余呉バスは市民の手でつくられた高齢化する余呉の足を支え続ける会社です。日常で走られている路線を含めた余呉の素敵なスポットを案内いただきました。

[余呉バスにて ウッディパル余呉の前川さん案内風景]

[地域の足を支える余呉バスを体験!余呉バスから降りる塾生]
バスガイドをしていただいた方は、余呉の観光拠点であるウッディパル余呉の支配人、前川和彦さん。
これまたスペシャルなガイドです。
余呉の歴史的スポットを要所要所で熱く案内いただく姿は、地域づくりの情熱を感じさせていただけました。
本当にありがとうございました。

[洞寿院入口にて前川さんの説明風景]

[特別企画!塾生の小野さん現地コーディネートで全長寺の住職さんより説明いただきました!]
昼食は午後からの講義、そして宿泊先になるウッディパル余呉の森林文化交流センターで。
これまたスペシャルな企画で、余呉の地域資源である余呉トレイルを歩きにきた観光客に出しているトレイル弁当を
体験させていただきました。多くの地元料理がたくさんつまったお弁当で工夫が万歳!

[トレイル弁当。盛りだくさんです!]
お腹がいっぱいになったあとは、すぐに講座がはじまります。
まずは、余呉における地域づくりを担われている地域プロデューサー方々から3人続けての講義。
濃い時間が続きます。
ウッディパル余呉の前川和彦さん、余呉オペラ実行委員会の横山義淳さん、株式会社余呉バスの木下重樹さん。
3人の方々は分野も年齢も組織の形態も全然違いますが、それぞれが余呉に熱い思いをもっておられ、
地域の課題解決のために事業をおこなっておられました。

[ウッディパル余呉 支配人 前川和彦さん講義]

[余呉オペラ実行委員会/べんがら座 主宰 横山義淳さん講義]

[株式会社余呉バス 代表取締役 木下重樹さん講義]
その後は、おうみ未来塾アドバイザーの法政大学教授の岡崎昌之先生から全国の事例をご紹介いただきながらの地域プロデューサーの考え方について学ばせていただきました。岡崎先生は、地域づくりは集落単位で考えることが大切、とおっしゃられ塾生もそれぞれの自分の地域のことを思い考えていたと思います。岡崎先生は、11期生のときも余呉での講座でお世話になりましたが、今回も朝からバスに乗り込んでいただきじっくり余呉講座に参加いただきました。

[岡崎先生 講義 テーマは地域プロデューサーを考える]
講義を聞いたあとは講師の先生方と塾生のディスカッションです。
みなさん積極的に地域をプロデュースるということについて考え方を共有し深めていきました。

[質問をする塾生]

[それに答える講師の方々]

[記念撮影]
全体塾生会を行い、その後は、せっかくの合宿という時間をみんなの距離を近づけるために自己紹介をじっくり行い、有意義な時間になりました。おうみ未来塾では2年目は、このメンバーでグループにわかれて活動していいくので、しっかりと自己紹介をしてお互いのことを知っておく必要があると考え塾生自らが企画していきました。
一人3分ということでとても短い時間でしたが、それぞれの個性が飛び交うとてもよい自己紹介ばかりでした。

[自己紹介を担当するAグループの司会進行ではじまりました!]

[サラ○パンな塾生も!]

[ピアノで自己紹介する塾生も!]
その後はご飯を食べながら語らい、夜が更けていったのでした。

[みんなで夕食の準備!]

[みんなでいただきます!]
[ ]
]
[夕食。]
一日目は、これで終わり、2日目は、朝から特別企画の朝ヨガ!目覚めの一発ということで、12期生でヨガインストラクターの小林さんがじっくり朝ヨガをしてくださいました。みんな気持ちのよい顔されてましたね。

[朝ヨガ風景]
朝から余呉にある廃校になった小学校を使い不登校支援をされているNPO法人子ども自立の郷ウォームアップスクールここからさんを訪れました。
ここからの理事長の唐子恵子さんからの活動紹介にはじまり、建物の紹介などをしていただきました。
特に唐子さんの事業をはじめるにいたった思い、はじめるためのいろんな経験は塾生のみなさんも真剣に耳を傾けられていました。

[理事長 唐子 恵子さんより講演]

[校舎の見学]
[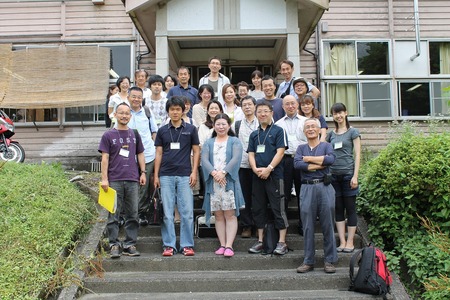 ]
]
[唐子理事長囲んでの記念撮影]
その後、場所を前日の横山さんが管理されている、べんがら座を見学して全体塾生会を行いました。
べんがら座は旧の木造の公民館を改装された小劇場。アートで地域づくりの拠点となっています。

[べんがら座]

[横山住職囲んでの記念撮影]
そしてお昼は、塾生企画で、古民家を小劇場として改装されている余呉小劇場弥吉で地元料理を食べました。
また、今回の講座の大テーマである「地域プロデューサーを考える」というテーマでグループごとに分かれてワークショップを行いました。自分達のこれから発見していく地域課題や、その課題を解決していくために必要な人材像について議論しました。

[グループごとにワークショップの発表の図]
これからの12期生は様々なフィールドで実践をとおして学び、2年目のグループ活動にむけて準備していきます。
みなさまどうぞよろしくお願い致します。
7/21、22と2日間にかけて、おうみ未来塾12期生の合宿をしてきました。
場所は長浜市余呉町。長浜市に合併をした余呉町では、市民によるまちづくりが活発に行われています。
今回のテーマは、「地域プロデューサーを考える」。
様々な余呉における地域プロデューサーの事例を見せていただきながら
塾生同士で地域プロデューサーとは何かを考える濃い2日間となりました。
一日目の午前中は、株式会社余呉バスに乗り込み、余呉のまちを見ていきます。
余呉バスの社長 木下さんに自ら運転いただく未来塾ならではのスペシャルなフィールドワーク。
公共交通は、経営難で撤退していく現実もあるなか、余呉バスは市民の手でつくられた高齢化する余呉の足を支え続ける会社です。日常で走られている路線を含めた余呉の素敵なスポットを案内いただきました。

[余呉バスにて ウッディパル余呉の前川さん案内風景]

[地域の足を支える余呉バスを体験!余呉バスから降りる塾生]
バスガイドをしていただいた方は、余呉の観光拠点であるウッディパル余呉の支配人、前川和彦さん。
これまたスペシャルなガイドです。
余呉の歴史的スポットを要所要所で熱く案内いただく姿は、地域づくりの情熱を感じさせていただけました。
本当にありがとうございました。

[洞寿院入口にて前川さんの説明風景]

[特別企画!塾生の小野さん現地コーディネートで全長寺の住職さんより説明いただきました!]
昼食は午後からの講義、そして宿泊先になるウッディパル余呉の森林文化交流センターで。
これまたスペシャルな企画で、余呉の地域資源である余呉トレイルを歩きにきた観光客に出しているトレイル弁当を
体験させていただきました。多くの地元料理がたくさんつまったお弁当で工夫が万歳!

[トレイル弁当。盛りだくさんです!]
お腹がいっぱいになったあとは、すぐに講座がはじまります。
まずは、余呉における地域づくりを担われている地域プロデューサー方々から3人続けての講義。
濃い時間が続きます。
ウッディパル余呉の前川和彦さん、余呉オペラ実行委員会の横山義淳さん、株式会社余呉バスの木下重樹さん。
3人の方々は分野も年齢も組織の形態も全然違いますが、それぞれが余呉に熱い思いをもっておられ、
地域の課題解決のために事業をおこなっておられました。

[ウッディパル余呉 支配人 前川和彦さん講義]

[余呉オペラ実行委員会/べんがら座 主宰 横山義淳さん講義]

[株式会社余呉バス 代表取締役 木下重樹さん講義]
その後は、おうみ未来塾アドバイザーの法政大学教授の岡崎昌之先生から全国の事例をご紹介いただきながらの地域プロデューサーの考え方について学ばせていただきました。岡崎先生は、地域づくりは集落単位で考えることが大切、とおっしゃられ塾生もそれぞれの自分の地域のことを思い考えていたと思います。岡崎先生は、11期生のときも余呉での講座でお世話になりましたが、今回も朝からバスに乗り込んでいただきじっくり余呉講座に参加いただきました。

[岡崎先生 講義 テーマは地域プロデューサーを考える]
講義を聞いたあとは講師の先生方と塾生のディスカッションです。
みなさん積極的に地域をプロデュースるということについて考え方を共有し深めていきました。

[質問をする塾生]

[それに答える講師の方々]

[記念撮影]
全体塾生会を行い、その後は、せっかくの合宿という時間をみんなの距離を近づけるために自己紹介をじっくり行い、有意義な時間になりました。おうみ未来塾では2年目は、このメンバーでグループにわかれて活動していいくので、しっかりと自己紹介をしてお互いのことを知っておく必要があると考え塾生自らが企画していきました。
一人3分ということでとても短い時間でしたが、それぞれの個性が飛び交うとてもよい自己紹介ばかりでした。

[自己紹介を担当するAグループの司会進行ではじまりました!]

[サラ○パンな塾生も!]

[ピアノで自己紹介する塾生も!]
その後はご飯を食べながら語らい、夜が更けていったのでした。

[みんなで夕食の準備!]

[みんなでいただきます!]
[
 ]
][夕食。]
一日目は、これで終わり、2日目は、朝から特別企画の朝ヨガ!目覚めの一発ということで、12期生でヨガインストラクターの小林さんがじっくり朝ヨガをしてくださいました。みんな気持ちのよい顔されてましたね。

[朝ヨガ風景]
朝から余呉にある廃校になった小学校を使い不登校支援をされているNPO法人子ども自立の郷ウォームアップスクールここからさんを訪れました。
ここからの理事長の唐子恵子さんからの活動紹介にはじまり、建物の紹介などをしていただきました。
特に唐子さんの事業をはじめるにいたった思い、はじめるためのいろんな経験は塾生のみなさんも真剣に耳を傾けられていました。

[理事長 唐子 恵子さんより講演]

[校舎の見学]
[
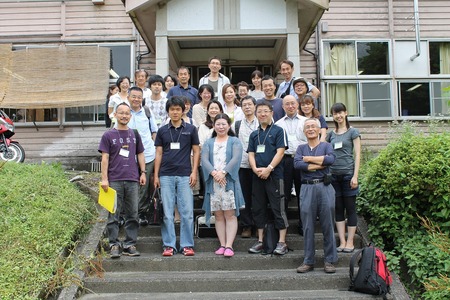 ]
][唐子理事長囲んでの記念撮影]
その後、場所を前日の横山さんが管理されている、べんがら座を見学して全体塾生会を行いました。
べんがら座は旧の木造の公民館を改装された小劇場。アートで地域づくりの拠点となっています。

[べんがら座]

[横山住職囲んでの記念撮影]
そしてお昼は、塾生企画で、古民家を小劇場として改装されている余呉小劇場弥吉で地元料理を食べました。
また、今回の講座の大テーマである「地域プロデューサーを考える」というテーマでグループごとに分かれてワークショップを行いました。自分達のこれから発見していく地域課題や、その課題を解決していくために必要な人材像について議論しました。

[グループごとにワークショップの発表の図]
これからの12期生は様々なフィールドで実践をとおして学び、2年目のグループ活動にむけて準備していきます。
みなさまどうぞよろしくお願い致します。
2012年07月07日
おうみ未来塾12期生第二回世話人会開催しました!
スタッフの膽吹(いぶき)です。
7月6日(金)守山市民交流センター 交流室にて
おうみ未来塾12期生の第二回世話人会を開催しました。
世話人会とはなにか?
おうみ未来塾は塾生が主体的に塾の運営をしていく塾です。
そのために、一年目の講座が続く基礎実践コースでは、地域ごとのグループにわかれて、
その中の世話人が集まって講座の企画などを話し合っていくのです。
もちろん30人塾生がいますから世話人会では、全体塾生会でどんなこと話そうかね~と企画を考えるところ。
全体塾生会は主に講座のあとにあるホームルームのようなもので全員が集うところです。
世話人会は、別になにかかたい権限のある代表の集まりというわけではないので、
世話人ではない塾生も集まります。
こういう場が交流の機会になったり、塾の運営についての議論が学びになったりするのでいいですね♪
今回の世話人会もわきあいあいと話し合いました♪
内容は主に今度の第二回本講座の合宿の内容について。
他は、塾運営の基本的な仕組みについてもどうしようか~と話し合いました。
焦点は2年目の創造実践コースグループ活動のこと。
これがこの塾の肝。みんなで話し合ってこの課題について、この地域で、このテーマで取り組もうと決めていきます。
そしてグループに分かれていきます。分かれ方も話し合う。
みなさん個人として、こんな地域プロデューサーになりたい、
こんなことをしたいという思いを持って入塾されたかたがほとんどの中
グループをつくり活動するというプロセスを実践を通して学びます。
今から、全体塾生会の時間をつかってどうやってグループをつくっていこうかというプランの
たたき台についても世話人会で話しました。
さぁこれから楽しみですね。みなさん12期生の活動をお見逃しなく~。
応援よろしくお願い致します(*^_^*)

[世話人会の風景。円卓会議です。]
7月6日(金)守山市民交流センター 交流室にて
おうみ未来塾12期生の第二回世話人会を開催しました。
世話人会とはなにか?
おうみ未来塾は塾生が主体的に塾の運営をしていく塾です。
そのために、一年目の講座が続く基礎実践コースでは、地域ごとのグループにわかれて、
その中の世話人が集まって講座の企画などを話し合っていくのです。
もちろん30人塾生がいますから世話人会では、全体塾生会でどんなこと話そうかね~と企画を考えるところ。
全体塾生会は主に講座のあとにあるホームルームのようなもので全員が集うところです。
世話人会は、別になにかかたい権限のある代表の集まりというわけではないので、
世話人ではない塾生も集まります。
こういう場が交流の機会になったり、塾の運営についての議論が学びになったりするのでいいですね♪
今回の世話人会もわきあいあいと話し合いました♪
内容は主に今度の第二回本講座の合宿の内容について。
他は、塾運営の基本的な仕組みについてもどうしようか~と話し合いました。
焦点は2年目の創造実践コースグループ活動のこと。
これがこの塾の肝。みんなで話し合ってこの課題について、この地域で、このテーマで取り組もうと決めていきます。
そしてグループに分かれていきます。分かれ方も話し合う。
みなさん個人として、こんな地域プロデューサーになりたい、
こんなことをしたいという思いを持って入塾されたかたがほとんどの中
グループをつくり活動するというプロセスを実践を通して学びます。
今から、全体塾生会の時間をつかってどうやってグループをつくっていこうかというプランの
たたき台についても世話人会で話しました。
さぁこれから楽しみですね。みなさん12期生の活動をお見逃しなく~。
応援よろしくお願い致します(*^_^*)
[世話人会の風景。円卓会議です。]