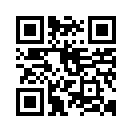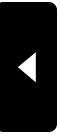2010年07月31日
日本NGO支援無償資金協力
◇対象となる団体:本制度に対して事業の申請ができるのは、以下のすべてを満たした団体です。
・日本のNGO(登記上、法人本部の住所が日本国内にある特定非営利活動法人または公益法人[財団法人、社団法人])であること。
※団体の本部が、同団体の定款、またはこれに類する規定において日本国内にあること、かつ日本国内にある上記事務所が、①事業、スタッフの雇用・その他の人事及び財務処理の統括、②資金調達活動・広報活動を行っているなど、実質的な本部機能を有していることが必要。
・法人格(NPO法人、公益法人[財団法人、社団法人])を有すること。
・任意団体の期間も含め、団体として2年以上の活動実績があること。
・国際協力活動の実施が団体の主要な設立目的の一つとなっていること。
・非合法的行為・反社会的行為等を目的とする団体でないこと。
・政治的、宗教的活動を主たる目的とする団体でないこと。
・営利活動を目的としていないこと。
・自ら供与対象事業の主要部分を実施すること。
※事業実施は現地のカウンターパートなど他団体が行い、日本のNGOは政府から資金を調達することが役割、というような場合には本制度の対象となりません。
・累積赤字を有している等の財務上の不安定要因を抱えておらず、また、予算書、決算書等の財務諸表が然るべく整備されている等、適切な会計処理及びその透明性の確保が図られていること(多額の公的資金を事前に提供するので、この項目は厳重
に審査されます)。
・過去1年以内に不適正な資金の使用により贈与資金の返還を行ったことがないこと。
◇対象となる事業
Ⅰ.開発協力事業:開発途上国(以下途上国)・地域の経済・社会開発を目的として、草の根の住民レベルに直接裨益する、日本のNGOが現地において実施する比較的小規模な事業に対して資金
面での協力を行うものです。
Ⅱ.NGOパートナーシップ事業:日本のNGOが日本国内外のNGOと2団体以上で連携・協同し、上記.Ⅰの開発協力事業等を実施するものです。複数のNGOの中で契約総額の50%以上を受け取る日本のNGOが主契約者となり、主契約者となった団体が贈与契約(G/C)の当事者となります。
Ⅲ.リサイクル物資輸送:日本の地方自治体や医療機関、教育機関などが提供する優良な中古物資等(消防車、救急車、病院用ベッド、車椅子、学校用机・椅子、仮設プレハブ住宅等の耐久消費財が対象で、食料、古着、文房具などの消耗品や個人の所有となる物資は対象となりません)を、開発途上国において日本のNGOが受け取り、当該途上国のNGO、地方公共団体等に贈与するにあたり、その輸送費等について資金面での協力を行うものです。
※なお、援助物資を当該途上国において受け取る者が、その国のNGOや地方公共団体等である場合には、本制度は利用できません。この場合、巻末の他の制度か、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の利用が考えられます。後者の場合は、申請書は途上国の引き受け(受け取り)団体より、わが方在外公館に対して提出いただく他、別途審査の基準が定められていますので、詳細は事業地の在外公館あるいは外務省・無償資金協力課に照会下さい。
Ⅳ.NGO緊急人道支援活動:海外で発生する大規模な武力紛争や自然災害に伴う難民・避難民・被災民に対する緊急人道支援活動を日本のNGOが行う場合、資金面での協力を行うものです。
Ⅴ.対人地雷関係事業:日本のNGOが行う地雷・不発弾処理、犠牲者支援、地雷回避教育といった対人地雷関連の活動について資金面での協力を行うものです。
Ⅵ.マイクロクレジット原資事業:貧困層の人々に少額・無担保の貸付を行う(マイクロクレジット事業)日本のNGOに対して、マイクロクレジットの原資となる資金を提供するものです。
<事業についての注意>
上記Ⅰ~Ⅴのいずれにあっても、以下の条件を満たす必要があります。
(1)申請団体が国外で自ら行う事業であること。
(2)日本政府のODA政策に沿う事業内容であること(提供される資金はODA[政府開発援助資金]です)。
(2)現地の国・地域における我が国の援助政策に沿った内容であること。
(3)現地の地域住民のニーズを十分に踏まえ、地域社会の経済・社会開発、民生の安定に役立つこと。
(4)地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること。
(5)環境面、人道面、ジェンダーの観点等で十分な配慮がなされていること。
◇事業を実施できる国・地域
(1)別紙1.で掲げられた国及び地域が対象となります。
(2)別紙1.の国・地域であっても、以下の危険度が高い国・地域や、現実的に日本のNGOの活動が困難な国・地域を除きます。
◆邦人に退避勧告が発出されている地域(緊急人道支援実施時及び一部地域を除く)
◆現地での日本のNGOの活動が非合法とされている場合(事前によく現地にご確認下さい)
<注意:その他に、現地当局へのNGO団体登録が求められる国もありますので、事前に良くご確認下さい。登録が困難なら、申請はできません。>
◇資金提供の対象となる経費:
(1)対象となる経費については、ホームページの「Ⅰ.開発協力事業」など各事業メニューの章を御参照下さい。
申請の際、以下の書類を提出して下さい。
日本NGO支援無償資金協力の実施要領、及び申請に必要な書類の様式は外務省ホームページ(ODAホームページ)で閲覧、ダウンロードが可能です。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html ※別ウィンドウで開きます)
申請先及び申請に関する問い合わせ先
(イ)日本で申請する場合:外務省経済協力局民間援助支援室(担当NGO支援班)
住所:〒105-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
TEL:03-5501-8000(ダイヤル・イン) 内線5768、5869、5883
FAX:03-5501-8360
(ロ)海外で申請する場合:事業実施国にある日本大使館・総領事館
◎この「手引き」、申請に必要な書類の様式は、外務省ホームページで閲覧・ダウンロードできます。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html ※別ウィンドウで開きます)
◎日本大使館・総領事館の連絡先も、外務省ホームページで閲覧できます。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html ※別ウィンドウで開きます)
ホームページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/kaikaku/oda_ngo.html
・日本のNGO(登記上、法人本部の住所が日本国内にある特定非営利活動法人または公益法人[財団法人、社団法人])であること。
※団体の本部が、同団体の定款、またはこれに類する規定において日本国内にあること、かつ日本国内にある上記事務所が、①事業、スタッフの雇用・その他の人事及び財務処理の統括、②資金調達活動・広報活動を行っているなど、実質的な本部機能を有していることが必要。
・法人格(NPO法人、公益法人[財団法人、社団法人])を有すること。
・任意団体の期間も含め、団体として2年以上の活動実績があること。
・国際協力活動の実施が団体の主要な設立目的の一つとなっていること。
・非合法的行為・反社会的行為等を目的とする団体でないこと。
・政治的、宗教的活動を主たる目的とする団体でないこと。
・営利活動を目的としていないこと。
・自ら供与対象事業の主要部分を実施すること。
※事業実施は現地のカウンターパートなど他団体が行い、日本のNGOは政府から資金を調達することが役割、というような場合には本制度の対象となりません。
・累積赤字を有している等の財務上の不安定要因を抱えておらず、また、予算書、決算書等の財務諸表が然るべく整備されている等、適切な会計処理及びその透明性の確保が図られていること(多額の公的資金を事前に提供するので、この項目は厳重
に審査されます)。
・過去1年以内に不適正な資金の使用により贈与資金の返還を行ったことがないこと。
◇対象となる事業
Ⅰ.開発協力事業:開発途上国(以下途上国)・地域の経済・社会開発を目的として、草の根の住民レベルに直接裨益する、日本のNGOが現地において実施する比較的小規模な事業に対して資金
面での協力を行うものです。
Ⅱ.NGOパートナーシップ事業:日本のNGOが日本国内外のNGOと2団体以上で連携・協同し、上記.Ⅰの開発協力事業等を実施するものです。複数のNGOの中で契約総額の50%以上を受け取る日本のNGOが主契約者となり、主契約者となった団体が贈与契約(G/C)の当事者となります。
Ⅲ.リサイクル物資輸送:日本の地方自治体や医療機関、教育機関などが提供する優良な中古物資等(消防車、救急車、病院用ベッド、車椅子、学校用机・椅子、仮設プレハブ住宅等の耐久消費財が対象で、食料、古着、文房具などの消耗品や個人の所有となる物資は対象となりません)を、開発途上国において日本のNGOが受け取り、当該途上国のNGO、地方公共団体等に贈与するにあたり、その輸送費等について資金面での協力を行うものです。
※なお、援助物資を当該途上国において受け取る者が、その国のNGOや地方公共団体等である場合には、本制度は利用できません。この場合、巻末の他の制度か、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」の利用が考えられます。後者の場合は、申請書は途上国の引き受け(受け取り)団体より、わが方在外公館に対して提出いただく他、別途審査の基準が定められていますので、詳細は事業地の在外公館あるいは外務省・無償資金協力課に照会下さい。
Ⅳ.NGO緊急人道支援活動:海外で発生する大規模な武力紛争や自然災害に伴う難民・避難民・被災民に対する緊急人道支援活動を日本のNGOが行う場合、資金面での協力を行うものです。
Ⅴ.対人地雷関係事業:日本のNGOが行う地雷・不発弾処理、犠牲者支援、地雷回避教育といった対人地雷関連の活動について資金面での協力を行うものです。
Ⅵ.マイクロクレジット原資事業:貧困層の人々に少額・無担保の貸付を行う(マイクロクレジット事業)日本のNGOに対して、マイクロクレジットの原資となる資金を提供するものです。
<事業についての注意>
上記Ⅰ~Ⅴのいずれにあっても、以下の条件を満たす必要があります。
(1)申請団体が国外で自ら行う事業であること。
(2)日本政府のODA政策に沿う事業内容であること(提供される資金はODA[政府開発援助資金]です)。
(2)現地の国・地域における我が国の援助政策に沿った内容であること。
(3)現地の地域住民のニーズを十分に踏まえ、地域社会の経済・社会開発、民生の安定に役立つこと。
(4)地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること。
(5)環境面、人道面、ジェンダーの観点等で十分な配慮がなされていること。
◇事業を実施できる国・地域
(1)別紙1.で掲げられた国及び地域が対象となります。
(2)別紙1.の国・地域であっても、以下の危険度が高い国・地域や、現実的に日本のNGOの活動が困難な国・地域を除きます。
◆邦人に退避勧告が発出されている地域(緊急人道支援実施時及び一部地域を除く)
◆現地での日本のNGOの活動が非合法とされている場合(事前によく現地にご確認下さい)
<注意:その他に、現地当局へのNGO団体登録が求められる国もありますので、事前に良くご確認下さい。登録が困難なら、申請はできません。>
◇資金提供の対象となる経費:
(1)対象となる経費については、ホームページの「Ⅰ.開発協力事業」など各事業メニューの章を御参照下さい。
申請の際、以下の書類を提出して下さい。
日本NGO支援無償資金協力の実施要領、及び申請に必要な書類の様式は外務省ホームページ(ODAホームページ)で閲覧、ダウンロードが可能です。(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html ※別ウィンドウで開きます)
申請先及び申請に関する問い合わせ先
(イ)日本で申請する場合:外務省経済協力局民間援助支援室(担当NGO支援班)
住所:〒105-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
TEL:03-5501-8000(ダイヤル・イン) 内線5768、5869、5883
FAX:03-5501-8360
(ロ)海外で申請する場合:事業実施国にある日本大使館・総領事館
◎この「手引き」、申請に必要な書類の様式は、外務省ホームページで閲覧・ダウンロードできます。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html ※別ウィンドウで開きます)
◎日本大使館・総領事館の連絡先も、外務省ホームページで閲覧できます。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html ※別ウィンドウで開きます)
ホームページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/kaikaku/oda_ngo.html
2019 「東北3.11基金」 助成プログラム公募のご案内
「横寺敏夫 患者と家族の支援基金」 助成公募のご案内
第36回(2019年度)老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
2019年度(第49回)毎日社会福祉顕彰のご案内
第39回 緑の都市賞 みどりの活動を大募集
第30回 緑の環境プラン大賞 募集のお知らせ
「横寺敏夫 患者と家族の支援基金」 助成公募のご案内
第36回(2019年度)老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
2019年度(第49回)毎日社会福祉顕彰のご案内
第39回 緑の都市賞 みどりの活動を大募集
第30回 緑の環境プラン大賞 募集のお知らせ
Posted by 淡海ネットワークセンター at 21:04
│助成金情報